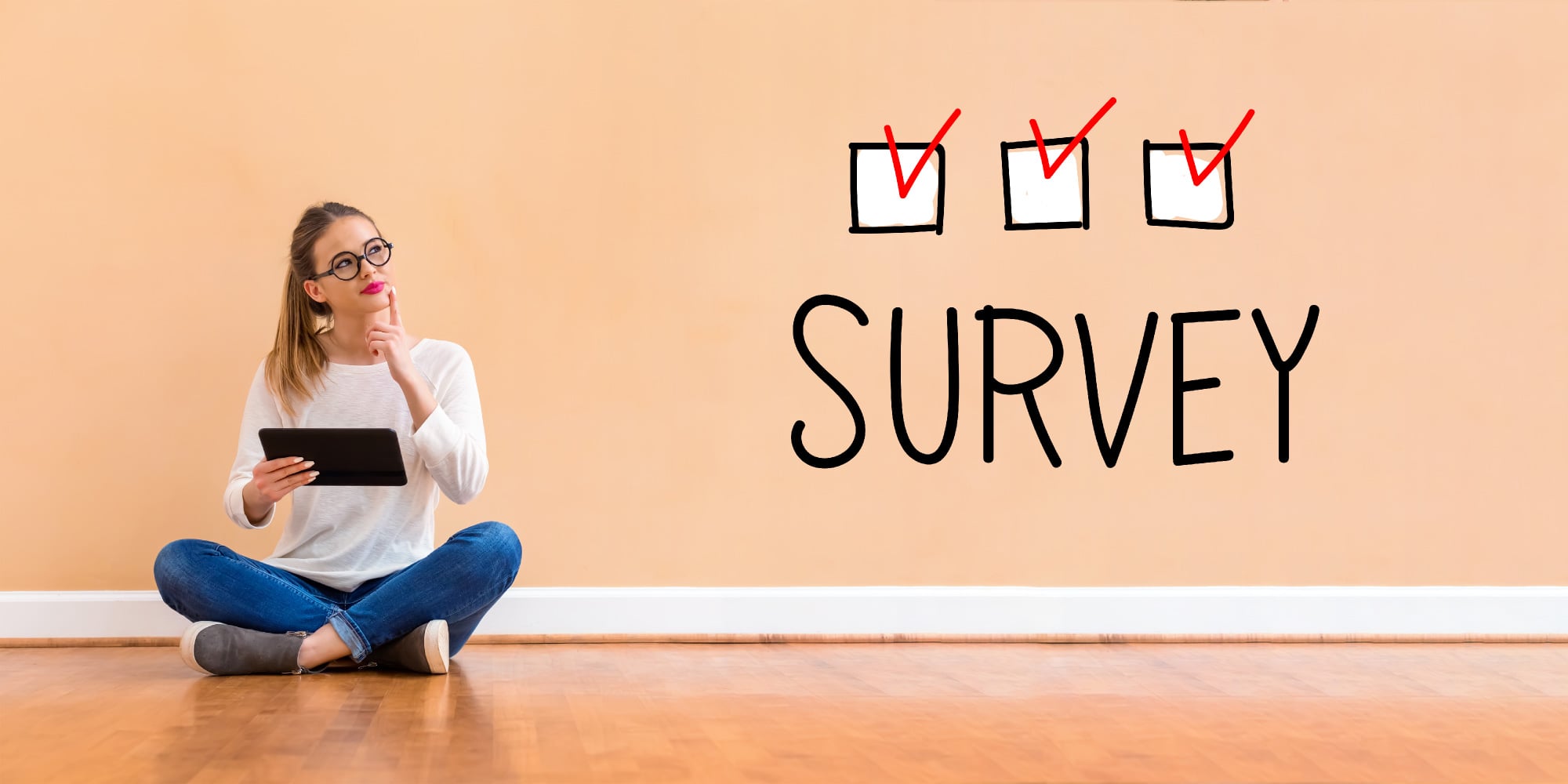従業員エンゲージメントとは
はじめに従業員エンゲージメントの概要をご紹介します。また、類似しているワーク・エンゲージメントについても解説します。
ワーク・エンゲージメント
ワーク・エンゲージメントとは、仕事に対するポジティブな心理状態のことで、仕事への活力や熱意、没頭によって特徴づけられます。活力は仕事に対して積極的に取り組むこと、熱意は仕事に対して誇りを持つこと、没頭は仕事に夢中になることを示します。
ワーク・エンゲージメントは組織に対してではなく、従業員自身が自分の仕事に対してどれほどポジティブであるかを示すものです。
従業員エンゲージメント
従業員個人に関するワーク・エンゲージメントから、組織に対するエンゲージメントが注目されるようになりました。従業員エンゲージメントとは、従業員が企業理念や戦略などを理解して、そこに向かって自らのスキルや能力を発揮しようとする貢献意欲です。
従業員エンゲージメントは、企業が目指すべき方向性を正しいと感じて、組織への愛着心を持つこと、そして自ら求められている以上のことを自立的に行うことで特徴づけられます。そのため、従業員エンゲージメントは、企業と従業員の相互の信頼関係などと表現する場合があります。
日本の従業員エンゲージメントは低い
日本人の民族性などを鑑みると、従業員エンゲージメントが高いイメージを持つかもしれません。しかし、日本の従業員エンゲージメントは国際的に見ても低いといえます。
これまでの日本企業は終身雇用や年功序列などによる給与体系が根付いていました。そのため、従業員は企業に対しての忠誠心が高い傾向でした。しかし、終身雇用や年功序列の精度が崩壊しつつあり、中高年の早期退職勧奨・賃金カットが珍しくありません。
非正規職員の割合も低いとはいえません。このような時代背景を仕方なしとしていると、従業員エンゲージメントが下がり、業績低下という事態を招く可能性があります。
従業員エンゲージメントが日本で浸透するまでの流れ
近年になり従業員エンゲージメントへの注目が高まってきています。日本で従業員エンゲージメントが浸透するまでの流れを2つに分けてご紹介します。
顧客から従業員の満足度を重視
ほとんどの企業には「顧客第一主義」という言葉が今も根付いているでしょう。これは日本古来の商人の魂が受け継がれているからです。商人は顧客の要望を叶えるという精神を持っています。
日本は商人の魂によって高度経済成長期にはものづくりの文化が形成されています。しかし、バブルが崩壊すると企業間の激しい競争から顧客獲得に重点が置かれるようになります。
商品に付加価値を与えるサービスの提供がはじまり、一部の業界ではサービス残業が常習化しました。顧客第一主義の精神によって従業員を犠牲にしてしまったのです。そして、着手したのが「従業員満足主義」です。
従業員の満足度からエンゲージメントへ
アメリカでは「従業員を第一に、顧客を第二に」という企業ポリシーを掲げる企業があり、黒字経営を継続させたケースがあります。
日本もそれにならって従業員満足主義を掲げる企業が増えています。この従業員満足主義は、給与や福利厚生、職場環境など企業が従業員に与えるものへの満足度を意味しています。
しかしながら従業員の主体的な行動に結びつかないことがあり、「エンゲージメント」が注目されるようになったのです。近年ではさまざまなメディアでもエンゲージメントが取り上げられるなど、注目度がさらに上がっています。
従業員エンゲージメントの向上には定期的なサーベイが必要
従業員エンゲージメントの注目度が高まり、各企業はさまざまな取り組みを考えているでしょう。しかし、エンゲージメントは目に見えずわかりにくいものです。そこで必要になるのが、定期的なサーベイです。
従業員それぞれのエンゲージメントレベルを把握することで、具体的な施策がわかってきます。エンゲージメントにおける評価指標(質問内容)の一例をご紹介します。
- 1.総合的な指標を調査する場合
- 「現在職探しをしている友人や家族に自社を勧めたいか?」
- 2.エンゲージメントレベルを調査する場合
- 「現在の自分の仕事にやりがいを感じるか?」
- 3.人間関係や職務の難易度を調査する場合
- 「企業全体の戦略目標を理解していますか?」
以上のような質問により従業員エンゲージメントが数値化できます。
従業員エンゲージメントサーベイのポイント
従業員エンゲージメントサーベイを行うときにおさえるべきポイントがあります。以下の3点を把握したうえで従業員エンゲージメントサーベイを行ってください。
従業員への説明
従業員エンゲージメントサーベイを実施するときは、対象となる従業員に説明を行ってください。「調査結果をどのように活かすのか」「誰からフィードバックがなされるのか」「回答結果を閲覧するのは誰なのか」などを周知しましょう。
適切な説明がないままにサーベイを実施すると、従業員から不信感を抱かれる可能性があります。結果として正直な回答が得られなくなることも考えられます。
特に回答結果が上司に閲覧されるとなると、評価への影響を懸念して素直な回答をしない場合があります。上司や同僚に回答結果が閲覧されないような配慮が必要です。
施策につなげる検討
従業員エンゲージメントサーベイは、企業の現状とその背景が明らかになります。ときには悪い結果として表れる場合もありますが、悪い状況に対して犯人捜しをするような行為は組織の改善につながりません。
調査結果をもとに改善策を考えることが重要です。そのためには経営層や担当部署だけではなく、従業員本人にも結果を開示する必要があります。
実施後のフィードバック
従業員エンゲージメントサーベイを実施して、従業員本人に結果を公開したら、フィードバックが必要です。フィードバックがあることで調査結果がどのように使われているかわかりやすくなります。
また、調査結果をもとに改善策を従業員に伝えることが大切です。企業として何をするのかを従業員に伝えることで信頼関係が構築できます。
従業員エンゲージメントサーベイの課題

従業員エンゲージメントサーベイを実施しても成果が不十分な場合があります。その際はサーベイ自体に何かしらの課題が考えられます。よくある課題として6つの内容をご紹介します。
精度が低い
まずは設問内容(アンケート内容)の精度の低さです。抽象的な内容で質問してしまうと、エンゲージメントに関する具体的な情報収集ができなくなります。設問の設計で失敗すると、調査全体が無意味なものになりかねません。設問の設計は非常に重要なフェーズです。
結果に対する原因究明ができていない
従業員エンゲージメントは定性的な情報収集に重点を置く必要があります。数値では見えにくい従業員の生の声を引き出すことが必要だからです。しかし、設問内容が定量的なものばかりになると、原因究明がしにくくなります。
分析方法が限定的
サーベイによりさまざまなデータが集まっても、分析方法を限定的にすると適切な施策が検討できません。例えば、コミュニケーションの活性化で低いスコアが出たとします。通常であれば最優先の課題として施策を考えるでしょう。
しかし、違う角度から分析してみると、コミュニケーションの活性化以外の課題が浮き彫りになることがあります。どの課題を最優先とするのか、スコアだけではなく重要度など複数の軸でクロス分析をすることが適切な分析につながります。
施策の検討が不十分
従業員エンゲージメントサーベイは結果をもとに施策を実行して改善することが目的です。しかし、調査を行っても改善策の立案まで行えない企業が存在します。
その場合、調査自体が目的となってしまい、何度実施しても改善できません。サーベイが効果を発揮するような運用体制が求められます。
経営層との合意形成ができていない
サーベイを実施した後に企業の仕組みや制度を変更することもあるでしょう。そのため、経営層のコンセンサスが必要です。
特に企業規模が大きくなるほど、経営層との合意形成が不十分な場合があります。大規模な施策を展開するためには経営層との合意形成を意識してください。
フィードバックをしていない
先述のとおり、サーベイ後は従業員にフィードバックすることが大事です。従業員からすれば調査結果が気になるものです。結果をしっかりとフィードバックしないと、サーベイの調査結果が無意味なものになりかねません。
定期的に従業員エンゲージメントサーベイを実施しよう
企業が中長期的に成長をしていくには、従業員エンゲージメントを向上させる必要があります。そのためには定期的に従業員エンゲージメントサーベイを実施して、施策の実行と改善を繰り返すことが重要です。
OurEngageは個人と組織の両輪でエンゲージメントの向上を目指すサーベイです。従業員に対する定性的なデータをもとに分析して、エンゲージメントの向上につなげます。ご興味がある場合は、ぜひご相談ください。